◎ホーム → 山郷のみどころ → 福寿草と蛍の里 sitemap
 「おらほも見とくらい」
「おらほも見とくらい」

「おらほも見とくらい」:”私達のみどころもどうぞご覧下さい”【北信州の方言】
山郷のみどころのご案内

|
福寿草と蛍の里のご紹介
北信州高山村の久保地区は、観光案内にはありませんが、山郷の生活に密着した素朴な自然や文化を味わえます。
|
季節を彩る花々
- 福寿草
 北信州に遅い春が訪れると、雪が解けた畑のくろに、黄金色の福寿草が一斉に咲き出し、独特の香りが漂います。有毒な植物ですが、根は強心薬になるそうです。
北信州に遅い春が訪れると、雪が解けた畑のくろに、黄金色の福寿草が一斉に咲き出し、独特の香りが漂います。有毒な植物ですが、根は強心薬になるそうです。
「赤和観音のしだれ桜」から「水中のしだれ桜」に至る道は「信州桜めぐりトレッキング」のコースになっており、この道の両側の畑に福寿草がたくさん咲いています。なかでも勝山さんの畑はどこも大きな群落になっていて、足を止めてご覧になる方が絶えません。
当地区には普通のフクジュソウとミチノクフクジュソウの2種類が見られます。
【見頃:4月上旬〜下旬】 ミチノクフクジュソウの特集
- キバナノアマナ
 北国の代表的な春植物で、雪が消えるとすぐにりんご畑で咲き出します。
北国の代表的な春植物で、雪が消えるとすぐにりんご畑で咲き出します。
中には枯れ葉を突き破って顔を覗かせる元気な花もあります。
周囲の雑草が繁茂するようになるといつの間にか姿を消します。
関西などからこの花を目当てにはるばるお越しになる花好きの方が毎年いらっしゃいます。
【見頃:4月中旬】 キバナノアマナの特集
- カタクリ
 雪が消え残る雑木林を進むと、草野や雑木の根元でカタクリが春の太陽の光を独り占めしようと、懸命にピンクの花を開いています。
雪が消え残る雑木林を進むと、草野や雑木の根元でカタクリが春の太陽の光を独り占めしようと、懸命にピンクの花を開いています。
種が芽を出してから花が咲くまで7〜8年もかかり、球根は片栗粉の材料になるそうですが、深くてとても掘れません。
木々が葉を広げて光が当たらなくなると、短い春が終わります。
【見頃:4月中旬〜下旬】 カタクリの特集
- 育成広場の桜


善光寺平と北信五岳を見渡す高台に「育成広場」があり、オオヤマザクラや八重桜などいろいろな種類の桜が植えられています。
ふもとの桜が散ってから新緑の時期まで花を楽しむことができ、休日には、家族や仲間でお花見をする姿があります。
【見頃:4月下旬〜5月上旬】 オオヤマザクラの特集
- 月生線のヤマアジサイ


「育成広場」を過ぎて林道「月生線」を登っていくと、杉林の林縁や雑木林の中にヤマアジサイが様々な色と形の花を咲かせます。
【見頃:6月下旬〜8月上旬】 ヤマアジサイの特集
- 初秋に開くタマアジサイ


お盆になって秋風が吹くころタマアジサイの花が開きます。
【見頃:8月中旬〜9月上旬】 タマアジサイの特集
上に戻る
- 蛍の郷


梅雨どきになると、久保川に沿って久保区の入口から上流までたくさんのゲンジボタルが飛び交い、湧き水が流れている民家の庭先にはヘイケボタルが生息し、あちこちで幻想的な光の点滅を楽しむことができます。 区の中程に「蛍公園」があり、池のほとりにはお地蔵さんが佇んでいます。
区の中程に「蛍公園」があり、池のほとりにはお地蔵さんが佇んでいます。
 「蛍見にこねえ会」の皆さんや区民が環境整備に取り組み、分館が主催する蛍鑑賞会も行われています。
「蛍見にこねえ会」の皆さんや区民が環境整備に取り組み、分館が主催する蛍鑑賞会も行われています。
土用に入って暑くなるとゲンジボタルは姿を消し、ヘイケボタルだけになります。
蒸し暑い日の夕暮れに、日中の火照りが残る舗装道路に腰を下ろし、ラジオのナイターを聞きながら、缶ビール片手に蛍を眺める姿も見受けられます。
ある年の蛍鑑賞会で、蛍の光をながめながら乾いた喉を潤していたところ、梅雨の雲の切れ間から満月が顔を出して蛍の光が薄れてしまい、急遽、”お月見”に変更したこともありました。
「蛍見や転びながらもあれ蛍」一茶
【見頃:6月下旬〜8月中旬】
上に戻る
高杜(たかもり)神社
- 高杜神社
 高杜神社は、信州高井野村(旧・長野県上高井郡高井村、現・高山村高井)全体を氏子とする神社で、大同元年(806年)に社殿が建てられたと伝えられており、延長5年(927年)にまとめられた「延喜式」に名前が記載されているそうです。
高杜神社は、信州高井野村(旧・長野県上高井郡高井村、現・高山村高井)全体を氏子とする神社で、大同元年(806年)に社殿が建てられたと伝えられており、延長5年(927年)にまとめられた「延喜式」に名前が記載されているそうです。
現在の拝殿は天明3年(1783年)に初代・亀原和田四郎の手によって再建され、拝殿の中に安置されている本殿は嘉永元年(1848年)に三代目・亀原和太四郎によって再建されたもので、ともに高山村の有形文化財に指定されています。
- 鳥居
 高杜神社の参道入り口には、嘉永5年(1852年)に三代目・亀原和太四郎によって再建された鳥居が建っています。
高杜神社の参道入り口には、嘉永5年(1852年)に三代目・亀原和太四郎によって再建された鳥居が建っています。
総欅材で、幅は1丈3尺、高さが1丈8尺8寸の両部鳥居です。
- 門灯籠
 久保区は平成20年に鳥居の奥に門灯籠を常設しました。
久保区は平成20年に鳥居の奥に門灯籠を常設しました。
前面に「高杜神社」、背面に「護国敬神」と揮毫された障子戸は、秋の例大祭と6年ごとの御柱祭の間だけ立て、普段ははずしてあるため人目に触れる期間は限られています。
(以前は毎年10月16日の早朝に組み立て、10月17日の夕方もしくは10月18日の早朝に分解していました。)
- 杉並木
 高杜神社入り口の鳥居から拝殿まで杉並木が約250メートル続き、なかには樹齢400年以上の大木もあります。
高杜神社入り口の鳥居から拝殿まで杉並木が約250メートル続き、なかには樹齢400年以上の大木もあります。
真夏の木陰は昼寝に最適で、昭和30年代までは、この杉並木の下で小学校の体育の時間にスキーが行われていました。
平成19年には高山村の第1回景観賞に選定されています。
- 勝山
 神社の裏山は”勝山”で、古代、祖霊の座す(おわす)山として信仰され、のちに里を守る神、作神として信仰されたと考えられています。
神社の裏山は”勝山”で、古代、祖霊の座す(おわす)山として信仰され、のちに里を守る神、作神として信仰されたと考えられています。
かつて高杜神社の参道脇に居住しておられた神官は「勝山」氏で、現在も久保地区の半数のお宅が「勝山」姓であることから、地区の住民と古くから強い関わりを持っていたことが伺われます。
- 秋祭
- 毎年10月16日は例大祭前夜の宵祭りが行われ、「灯籠揃い」(とうろうぞろい、訛って”とうろぞれ”)には各氏子組から灯籠、獅子舞、御輿などが奉納されます。
境内には屋台が並び、村一番のにぎわいを見せます。
- 御柱(おんばしら)祭
- 高杜神社は諏訪大社(長野県諏訪市に上社、下諏訪町に下社のある神社の総称)の系列であり、寅と申の年には北信州で最大(自称)の御柱祭が行われます。
本家の諏訪大社では樅(もみ)の大木の御柱を神社の四隅に建てますが、高杜神社では松の御柱1本を社殿の前に、左右交互に建て、このほかに長持ち行列と宝船や屋形船などの山車や民謡流し、樽御輿、俵御輿などがにぎやかに繰り出します。
御柱祭の様子です。
「福寿草と蛍の郷」の道案内
「福寿草と蛍の郷」久保区の地図をご覧ください。
○久保地区は、”勝山”の裾に沿って、全長約1,200メートル、標高差約130メートルの坂道の両側に70戸弱の民家が連なる集落です。
久保地区の入口は村のスポーツパークで、トレーニングセンター、コミュニティーセンター、夜間照明付きのグランドとテニスコートがあります。

 コミュニティーセンターの反対側では、ステンレス製の「招き猫」や「福籠(ふくろう)」くんたちがご挨拶しています。勝山ステンレス工業さん(TEL:026-248-1673)が製作する猫たちはテレビでも紹介され、長野県内のあちこちで「傘立て」や「看板猫」として手を挙げています。
コミュニティーセンターの反対側では、ステンレス製の「招き猫」や「福籠(ふくろう)」くんたちがご挨拶しています。勝山ステンレス工業さん(TEL:026-248-1673)が製作する猫たちはテレビでも紹介され、長野県内のあちこちで「傘立て」や「看板猫」として手を挙げています。
 テニスコートの桜の木の下に「ホタルの郷」の案内標識とベンチ、石垣には地区の地図があります。
テニスコートの桜の木の下に「ホタルの郷」の案内標識とベンチ、石垣には地区の地図があります。
 テニスコートの隣は久保神社の境内で、ちょっとした公園になっており、東屋と久保神社の社殿があります。
テニスコートの隣は久保神社の境内で、ちょっとした公園になっており、東屋と久保神社の社殿があります。
 案内標識から100メートルほど進むと高杜神社の参道入り口で、大きな石の社標と鳥居があり、杉並木の奥に拝殿と社殿が見えます。
案内標識から100メートルほど進むと高杜神社の参道入り口で、大きな石の社標と鳥居があり、杉並木の奥に拝殿と社殿が見えます。
「水中のしだれ桜」の案内標識のある十字路を過ぎると上り坂になり、冬期間は積雪量が目に見えて増えるため、ここから先の住人の生活に4輪駆動車は必需品です。
車社会になる前の冬には、上の方に住む子ども達が手製の”そり”で道路を滑り下り、勝山哲さんのお宅の生け垣に”そり”を置いて学校に通っていました。
中には、勢いが余って寒中の川に突っ込む”そり”もありましたが、それでも懲りずに”そり”通学は続きました。
地区の入り口から500メートルほど進むと、道路は久保川と平行して上っていきます。
かつて久保川の川底には鰍(かじか)や沢ガニが住んでおり、子どもたちは石の下にいる鰍を捕まえて遊びましたが、今はコンクリートで固められ、こうした生物の姿を見ることはできなくなりました。
また、川に石がなくなり、大雨が降ると雨水が一気に下流に流れるようになって、蛍の幼虫や餌のカワニナまで流される恐れがあり、心配されます。
 「辻の家(つじのうち)」と呼ばれる窪田先生のお宅の角を曲がり、ぶどう畑の間の急な坂を上ると、みんなが「どうろくじん」とよんでいる道祖神があります。
「辻の家(つじのうち)」と呼ばれる窪田先生のお宅の角を曲がり、ぶどう畑の間の急な坂を上ると、みんなが「どうろくじん」とよんでいる道祖神があります。
”勝山”の裾に沿って道を上って行くと「十々木入(とときいり)」地籍に入ります。「十々」の本来の字は、「斗」の”ちょんちょん”の所が小さな「十」という珍しい字です。
「十々木入」の入り口にお住まいの十々木謙一郎さんは、「蛍見にこねえ会」の会長さんで、蛍の郷の整備に取り組んでおられます。
「十々木入」の奥には小さな”ため池”があり、鯉や金魚が泳いでいます。池のほとりには桜の木が植えてあり、300年後には桜の名所になっているかもしれません。
久保川に沿って林道・月生線(つきおいせん)を上ると「育成広場」に到着します。
遠くに見える北信越のやまなみは、ここまで登ってきた疲れを忘れさせます。

育成広場から見る秋の北アルプス白馬岳と北信越の山なみ
 育成広場の先の雑木林には、夏になると「オニムシ」と呼んでいるクワガタやカブトムシがクヌギの樹液を吸っています。
育成広場の先の雑木林には、夏になると「オニムシ」と呼んでいるクワガタやカブトムシがクヌギの樹液を吸っています。
上に戻る
交通のご案内
北信州高山村久保地区までの道順です
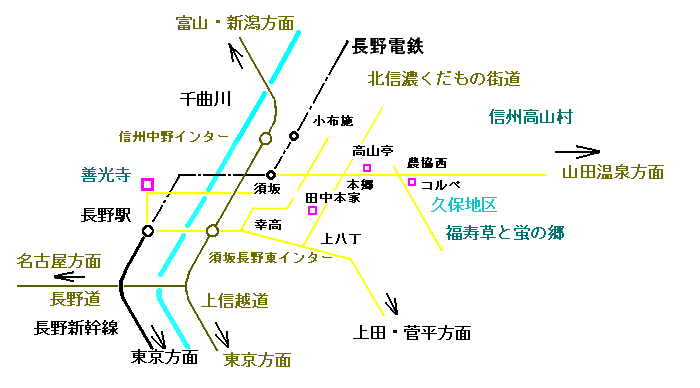
お車で
上信越道の須坂長野東インターを出て右折し、900メートル進みます。
”幸高町”の交差点を右折し、菅平方面に2.7キロメートル上ります。
”上八町”の交差点を左折し「北信濃くだもの街道」を道なりに4.9キロメートル北進します。
途中、桜の名所「臥竜公園」が左に見え、「豪商の館 田中本家博物館」入口の看板を左に見てトンネルを抜けると、右側の山裾には「須坂温泉」があります。
「信州高山温泉郷」の案内看板のある”本郷”交差点を右折します。
山田温泉方面に向かい、松林の中の「和食・そば処 高山亭(こうざんてい)」を左手に見て1.7キロメートル進み、”農協西”の信号を右折すると入り口です。
(距離は目安です)
電車・バスで
長野新幹線・長野駅で長野電鉄に乗り換え、須坂駅で降ります(約25分)。
「山田温泉」行きバスに乗り、「農協前」で降ります(約10分)。
30メートルほど下って”農協西”の信号を横断すると久保区の入り口です。
地元の住人は、1つ手前の「堀之内上」でバスを降り、「高杜神社参道」の標識のある郵便局前の道を上がります。
運賃が安く、時間は余り変わりません。
信号脇の「collPain(コルペ)」さんでは焼きたてのパンを販売しています。
大きな地図で見る
上に戻る
◎ホーム → 山郷のみどころ → 福寿草と蛍の里